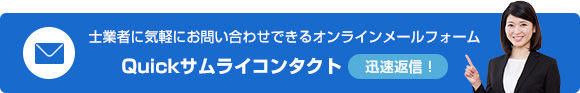BLOG
- トップページ >
- BLOG
中野人事法務事務所中野 泰(なかの やすし)
 ブログ記事一覧
ブログ記事一覧
【事業場外労働のみなし労働時間制とは?】
事業場外労働のみなし労働時間制とは、
従業員が業務の全部または一部を事業場外で従事し、
会社や上司の指揮監督が及ばないために、
その業務についての労働時間の算定が難しい場合に、
本来、会社に課せられている労働時間の算定義務を免除し、
その事業場外労働について「特定の時間」働いたものと
みなすことのできる制度です。
【事業場外労働のみなし労働時間の要件は?】
事業場外労働のみなし労働時間制の対象とするためには、
次の2つの要件を満たす必要があります。
1 労働時間の全部または一部を事業場外で業務に従事すること
2 会社や上司の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が難しいこと
次のように事業場外で従事する場合であっても、
会社や上司の指揮監督が及んでいる場合については、
労働時間の算定が可能ですので、みなし労働時間制の適用はできません。
1 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、
そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
2 携帯電話等によって随時使用者の指示を受けながら働いている場合
3 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、
指示通りに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合
新聞・雑誌の記者、直行直帰型の営業社員、
一般従業員の出張時等に適用されることが多いです。
【労働時間の算定方法は?】
事業場外労働のみなし労働時間制が適用される
事業場外の業務に従事した場合における労働時間の算定には、
次の3つの場合があります。
1 所定労働時間
2 事業場外の業務を遂行するためには、
通常所定労働時間を超えて働くことが必要である場合には
その業務の遂行に通常必要とされる時間
3 2の場合で労使協定が締結されている時は、
その協定により事業場の業務の遂行に
通常必要とする時間として定めている時間
ただし、2及び3の方法による場合で
「みなすことのできる労働時間」は
事業場外労働に該当する部分のみです。
労働時間の一部を事業場内で働いた場合には、
その時間については別途把握しなければならず、
「みなす」ことはできません。
したがって、労働時間の一部について
事業場外で業務に従事した日における労働時間は、
次の計算式となります。
みなし労働時間制により算定される業場外で業務に従事した時間
+ 別途把握した事業場内における時間
【1日における労働時間の算定方法は?】
こちらをクリックしてご確認ください。
【事業場外労働に関する労使協定について】
常態として行われている事業場外の業務であって
労働時間の算定が困難であり、
通常所定労働時間を超える場合は、
その業務について通常必要時間を労使協定書により定めると、
その協定で定める時間が通常必要時間となります。
労使協定の締結事項としては、下記の通りです。
1 対象とする業務
2 みなし労働時間
3 有効期間
さらに、下記のものについては就業規則で定めることで足りますが、
他の従業員と異なる扱いをする場合には、
労使協定で定めることになります。
4 時間外労働
5 休日労働
6 深夜労働
労使協定は従業員に周知しなければいけません。
また、その協定で定める時間が法定労働時間を超える場合には、
事業場外労働に関する協定届(様式第12号)を
事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出する必要があります。
なお、様式第9号の2の時間外労働に関する協定届を届け出ることにより
様式第12号に替えることができます。
<労働時間の全部について事業場外で働いた場合>
労使協定で定める時間は事業場外の業務についての通常必要時間となります。
<労働時間の一部について事業場外で労働した場合>
1 労使協定で定める時間と事業場内労働の時間を加えた時間が
所定労働時間を超える日
労使協定であらかじめ定めた時間が
事業場外労働の時間と算定されます。
この場合の労働時間は、労使協定で定めた事業場外労働の時間と
別途把握した事業場内労働の時間の合計となります。
2 労使協定で定める時間と事業場内労働の時間を加えた時間が
所定労働時間を超えない日
労使協定で定めた時間ではなく、
事業場外労働の労働時間は
事業場内労働の時間を含めて所定労働時間働いたものとみなします。
【時間外労働についての考え方】
事業場外労働のみなし労働時間制により算定されるみなし労働時間が
法定労働時間を超える場合には
法定労働時間を超えた時間は時間外労働となり、
2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。
(例:事業場外の業務に従事した時間と
別途把握した事業場内の業務に従事した時間の合計が
法定労働時間を超えた場合 等)
【休日労働についての考え方】
事業場外労働のみなし労働時間制により
労働時間が算定される場合であっても、
法定休日の規程は適用になります。
<法定休日に労働時間の全部が事業場外で業務に従事した場合>
その労働時間の算定が困難であり、
通常必要時間が所定労働時間以内であるときには、
所定労働時間働いたものとみなします。
その結果、所定労働時間に対して
3割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。
なお、休日労働の日の所定労働時間は
通常の労働日の所定労働時間によります。
<法定休日の労働時間の一部が事業場内労働である場合>
みなし労働時間制により算定される事業場外で業務に従事した時間と、
別途把握した事業場内における時間の合計に対して、
3割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。
<法定休日以外の所定休日労働の場合>
法定休日と同様に、所定休日労働の時間を算定してください。
法定労働時間を超える時間は時間外労働となります。
時間外労働と同様に割増賃金を支払う必要があります。
【深夜労働についての考え方】
事業場外労働のみなし労働時間であっても、
深夜労働の条文は適用されます。
午後10時から午前5時までの間に働いた時は、
その時間については2割5分増以上の割増賃金を支払う必要があります。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
1週間単位の非定型的変形労働時間制の概要は?
【1週間単位の非定型的変形労働時間制とは?】
30人未満の事業場である小売業・旅館・料理店・飲食店において、
業務の繁閑に応じて1週間単位で毎日の労働時間を柔軟に定めることができる制度です。
この制度を導入することで、
1週間40時間以内の範囲で1日の法定労働時間(8時間)を超える
所定労働時間を設定することができます。
週ごとに忙しい日と暇な日が異なる場合や、
日々の業務において繁閑の差が大きい等、
1週間ごとに労働時間を変更した方が効率がよい場合に適しています。
【導入するための要件】
1 労使協定を締結すること
労使協定は従業員に周知し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う必要があります。
2 就業規則を作成し、所轄労働基準監督署に届け出を行うこと
※1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施する旨を規定します。
※本来は就業規則の作成・届出義務がない従業員が常時9人以下の事業場についても
この制度を導入する場合は、就業規則を作成し、届け出ることになっています。
3 1週間の所定労働時間は40時間以内、1日は10時間を限度とすること
4 1週間の各日の労働時間を、その週の始まる前(前週末)までに
従業員に書面で通知すること
5 緊急でやむを得ない事由が生じた場合には既に通知した労働時間を、
変更しようとする日の前日までに書面により従業員に通知すること
(ただし、台風の接近等客観的事実により、
当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合はよいですが、
使用者の主観的な必要性である場合は認められません)
6 1週間の各日の労働時間を決めるにあたっては、従業員の意思を尊重するように努めること
なお、小売業・旅館・料理店・飲食店の事業のうち、
10人未満の事業場の1週間の法定労働時間は、週44時間となっていますが、
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、
この特例は適用されず、1週間40時間以内としなければなりません。
【就業規則に定めることは何?】
1週間単位の非定型的変形労働時間制は
各週ごとに各日の所定労働時間を定める制度です。
このため、就業規則においては、1週間の所定労働時間を定めて、
各日の始業・終業時刻及び休憩時間については、
従業員に通知する時期や方法などを規定することになります。
なお、業務ごとに勤務パターン、例えば、早出・中出・遅出が業務ごとに定められている場合は、
それぞれの業務ごとの勤務パターンにおける始業・終業時刻及び休憩時間も規定してください。
【割増賃金の支払いについて】
次の時間について時間外労働となり、割増賃金を支払うことが必要です。
1 従業員に対する通知により所定労働時間が8時間を超える日については
その所定労働時間を超えた時間、
所定労働時間が8時間以内の日については8時間を超えた時間
2 1週間については、40時間を超えた時間
(ただし、「1」で時間外労働となる部分は除きます)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
フレックスタイム制のメリットとデメリットは?
フレックスタイム制は従業員の意思で始業時刻と終業時刻を決められる点に特徴があります。
といっても、ある社員は早朝に来て昼過ぎに帰り、
別の社員は昼過ぎに来て夜に帰るような形になると、
会議もしづらくなってしまいます。
そこで、この時間帯は必ず在籍するようにという「コアタイム」を設け、
その前後にこの時間帯の範囲内で出社・退社してくださいという「フレキシブルタイム」を設けます。
コアタイムをあまり長くしすぎると、実質的にフレックスタイム制度の趣旨が損なわれることから、
だいたい4時間程度までをコアタイムとすることが多いです。
※昔、コアタイムを5時間にしたら、労基署から行政指導を受けたことがありました。
従業員にとっては、自分の意思で出社時刻や退社時刻が決められますので、
非常にメリットが大きい制度です。
しかも、1日8時間働かなくても、コアタイムの時間帯に在籍していれば、
遅刻・早退もありません。
コアタイムが4時間の会社の場合、月の半分はコアタイムの4時間のみ、
残り半分はコアタイムを含めて12時間働けば、平均8時間となります。
この場合、この人は(深夜や休日に仕事をしていなければ)
遅刻・早退・残業が一切ないとみなされ、
通常の月給をもらうことになります。
今日は早めに退社して、その分明日頑張ろうといった時間配分もできるわけです。
一方、会社側から見たらいかがでしょうか。
上記のメリットを従業員が享受することで、ライフワークバランスが取りやすくなり、
仕事に活力が生まれ、生産性が上がれば会社にとってもメリットとなります。
ただし、実は他の変形労働時間制と比較して、扱いづらい制度ではあります。
従業員が自主的に出社・退社時刻を決めるということは、
原則として「明日は9時に来なさい」等と言いづらくなることを意味しています。
(※ 絶対言えないということではありません。)
朝イチ全員で集まって早朝会議をすることもしづらくなり、
コアタイムの時間帯に会議を設定することが多くなってきます。
この時間帯はお客様とお目にかかったりすることも多いでしょうから、
コアタイムにも会議を入れづらくなるでしょう。
月曜日は通常の労働時間制度、他の日はフレックスタイム制といったように
曜日単位で変形労働時間制を導入することもできません。
要は、労働時間に関する権限の一部について、会社から従業員側に譲ることになるのです。
こうしたことにストレスを感じる経営者の方や、
これでは仕事が回らなくなるという会社の場合は、
導入を見送ることを検討した方がよいでしょう。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
フレックスタイム制の概要は?
【フレックスタイム制とは?】
フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、
従業員がその範囲内で、業務の繁閑などに合わせて、
各自の始業及び終業時刻を選択して働く制度です。
これにより、従業員はその生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことが可能となります。
このフレックス制による場合は、三六協定がなくても、
清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、従業員が選択することにより、
1日の労働時間帯を、コアタイムとフレキシブルタイムとに分け、
始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねることになります。
※ コアタイム:従業員が労働しなければならない時間帯
※ フレキシブルタイム:従業員の選択により労働することができる時間帯の中であれば
いつ出社または退社してもよい時間帯
なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、
1日の労働時間帯の全部をフレキシブルタイムとすることもできます。
逆に、1日の労働時間帯の中でコアタイムがほとんどを占め、
フレキシブルタイムが極端に短い場合は、
基本的に始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねたことにならず
フレックスタイム制とはみなされません。
(経験的にはコアタイムは4時間くらいまでが限度のようです。)
【要 件】
フレックスタイム制を採用するためには、次の要件を満たさなければなりません。
1 就業規則その他これに準ずるものにより、
始業・終業の時刻を従業員の決定に委ねる旨を定めること
2 書面による労使協定で、対象従業員の範囲や清算期間など、
次に説明する「労使協定で定めること」に掲げる事項を定めること
※ この労使協定は従業員に周知させなければなりません。
※ この労使協定を管轄の労働基準監督署へ届け出る義務はありません。
【労使協定で定める事項】
1 対象となる従業員の範囲
フレックスタイム制を適用する従業員の範囲を明確に定めることが必要です。
この場合、対象となる従業員の範囲を「全従業員」あるいは
「特定の職種の従業員」と定めることができます。
個人ごと、課ごと、グループごとなど様々な範囲も考えられます。
2 清算期間
A 清算期間は、フレックスタイム制において
労働契約上従業員があろうどうすべき期間を定めるもので、1ヶ月以内とされています。
「1ヶ月以内」ですから、1週間単位なども可能です。
ただし、賃金計算期間に合わせて1ヶ月とする場合が一般的です。
B 清算期間については、その長さと起算日を定めることが必要です。
単に「1ヶ月」とせず、毎月1日から月末までなどと定めることが必要です。
3 清算期間における総労働時間
A この時間は, 労働契約上従業員が清算期間内において
労働すべき時間として定められている時間のことで、
清算期間における所定労働時間のことです。
B この時間は、 清算期間を平均し、1週間の労働時間が
法定労働時間(原則40時間)の範囲内とするように定めることと要します。
その計算方法は、1ヶ月単位の変形労働時間制と原則として同様です。
清算期間における総労働時間≦40×(清算期間における暦日数/7)
=清算期間における法定労働時間の総枠
C 労使協定は, 清算期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、
例えば1ヶ月160時間というように
各清算期間を通じて一律の時間を定める方法の他、
清算期間における所定労働日を定め、
所定労働日1日当たり7時間というような定め方をすることもできます。
4 標準となる1日の労働時間
標準とのある1日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に支払われる
賃金の算定基礎となる労働時間等となる労働時間の長さを定めるものであり、
単に時間数を定めれば足りますが、
定め方としては、清算期間における総労働時間を
その期間における所定労働日数で除す方法などがあります。
なお、フレックスタイム制を採用している従業員がその清算期間内において、
有給休暇を取得したときには、その取得した日については、
標準となる労働時間を労働したものとして取り扱うことになります。
5 コアタイム・フレキシブルタイムの開始および終了の時刻
コアタイム・フレキシブルタイム等を設ける場合は、
必ず労使協定でその開始および終了時刻を定めることとされています。
【労働時間の算定等】
フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を
従業員の決定に委ねることになりますが、
その場合にも使用者は労働時間を把握する義務があり、
使用者は、各従業員の各日の労働時間を把握しなければなりません。
【労働時間の過不足の取り扱い】
実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べ
過不足が生じた場合には、
清算期間内で労働時間及び賃金を清算することが原則ですが、
次の清算期間に繰り越すことの可否については次の通りです。
1 実際の労働時間に過剰があった場合
結論:過剰分は残業代として支払うこと
清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、
総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払い日に支払うが、
それを超えて働いた時間分を、次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、
その清算期間内における労働の対価の一部が
その期間内の賃金支払い日に支払われないことになり、
賃金の全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反します。
2 実際の労働時間に不足があった場合
結論:一定条件の下、不足分を時月に繰り越すことができる
清算期間における労働時間に不足があった場合に、
総労働時間として定められた時間分の賃金は
その期間の賃金支払い日に支払うが、
それに達しない時間分を次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、
法定労働時間総枠の範囲内である限り、
その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、
次の清算期間で、その分の賃金の過払いを清算するものと考えられ、
賃金の全額払いの原則(労働基準法第24条)に違反するのではありません。
ただし、この場合には、繰り越された時間を加えた次の清算期間における労働時間が
法定労働時間の総枠の範囲内となるように、
繰り越しできる時間の限度を定める必要があります。
【時間外労働】
フレックスタイム制を採用した場合の時間外労働は1日及び1週間単位では判断せず、
清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。
したがって、時間外労働に関する協定についても、1日の延長時間について協定する必要はなく、
清算期間を通算しての延長時間および1年間の延長期間の協定をすれば足りることとなります。
なお、清算期間が1ヶ月で、清算期間を通じて完全週休2日制を実施している場合、
清算期間における曜日の巡りや労働日の設定によっては、
清算期間の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えることがありますが、
次の要件を満たす場合に限って、清算期間の労働時間が法定労働時間の枠を超える場合にも、
法定労働時間以内とみなす特別な取り扱いを認めています。
A 清算期間を1ヶ月とするフレックスタイム制の労使協定が締結されていること
B 清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること
C 特定期間(=その期間の29日目を起算日とする1週間)における
対象となる従業員の実際の労働日ごとの労働時間の和が
週の法定労働時間(40時間)を超えるものでないこと
D 清算期間における労働日ごとの労働時間が概ね一定であること。
したがって、完全週休2日制を採用する事業場における
清算期間中の労働日ごとの労働時間については、概ね8時間以下であること
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
1年単位の変形労働時間制の概要は?
【1年単位の変形労働時間制とは?】
なお、労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金の支払いを要する時間とは、
労使協定を締結することにより、1ヶ月を超え1年以内の一定期間を平均し、
1週間の労働時間を40時間以下の範囲以内にした場合、
特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
業務に繁閑のある事業場において、
繁忙期に長い労働委時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより
効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的にしたものです。
この労使協定は労働基準監督署長に届け出る必要があります。
1年単位の変形労働時間制を実施する時には、
書面による労使協定で次の5項目について定めることとされています。
1 対象労働者の範囲
2 対象期間及び起算日(対象期間:1ヶ月を超え1年以内の期間に限ります)
3 特定期間
4 対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間
5 労使協定の有効期間
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合は従業員に周知し、
所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
また、常時10人以上の従業員を使用している事業場については、
1年単位の変形労働時間制を採用すること等を就業規則に記載したうえで、
これを労働基準監督署長に届け出ることとされています。
【対象労働者の範囲は?】
1年単位の変形労働時間制により労働させる従業員の範囲を
労使協定で明確にしなければいけません。
なお、勤務期間が対象期間に満たない途中採用者・途中退職者等についても
賃金の精算を条件に本制度の適用が認められています。
【対象期間及び起算日は?】
変形労働時間制の対象期間は、その期間を平均して1週間当たりの労働時間が
40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、
1ヶ月を超え1年以内の期間に限ります。
最長期間は1年間です。
期間が1年以内であれば、3ヶ月、4カ月、半年等の対象期間を採用することも可能です。
【労働日と労働時間の特定について】
対象期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えないように
対象期間内の各日、各週の労働時間を定めることが必要です。
これは対象期間の全期間にわたって定めなければなりません。
ただし、対象期間を1ヶ月以上の期間に区分することとした場合には
下記の4点を定めればよいこととなっています。
1 最初の期間における労働日
2 最初の期間における労働日ごとの労働時間
3 最初の期間を除く各期間における労働日数
4 最初の期間を除く各期間における総労働時間
この場合でも、最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間については、
その期間の始まる少なくとも30日前に労働組合
(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表するもの)の同意を得て、
書面により定めなければいけません。
なお、対象期間を通した所定労働時間の総枠は、次の計算式によることになります。
対象期間における所定労働時間総枠≦40時間×(対象期間の暦日数/7)
※参考:対象期間が1年間の場合、約2085時間となります。
【労働日数の限度について】
対象期間における労働日数の限度は、原則として1年当たり280日となります
(対象期間が3ヶ月以内の場合は、制限はありません。)。
対象期間が3ヶ月を超え1年未満の場合は、下記計算式で上限日数が決まります。
通常の年は1年間で365日ですが、閏年は366日です。
計算式:280日×対象期間中の暦日数÷365日
例:対象期間が平成●年1月1日から6月30日までの6カ月(総暦日数181日)の場合は
280日×181日÷365日=138.84となり、138日が限度となります。
ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合であって、
前年度において、3ヶ月を超える期間を対象期間とする協定
(以下「旧協定」といいます)があった時は、
旧協定の1日または1週間の労働時間よりも新協定の労働時間を長く定め、
及び1日9時間または1週48時間を超えることとしたときは、
1年間の労働日数を280日または、旧協定の労働日数から1日を減じた日数のうち
いずれか少ない日数としなければいけません。
【対象期間における連続労働日数と特定期間について】
連続労働日数は原則として最長6日までです。
ただし、「特定期間」を設ければ1週間に1日の休日が確保できる日数(最長12日)
とすることができます。
なお、「特定期間」とは労使協定により対象期間のうち
特に業務が繁忙な時期として定められた期間をいいます。
【1日・1週間の労働時間の限度】
1年単位の変形労働時間制には、1日・1週(対象期間の初日の曜日を起算とする7日間。
以下同じ。)労働時間の限度が定められており、
1日10時間、1週52時間が限度時間です。
(隔日勤務のタクシー運転者の1日の限度時間は16時間です。)
この場合、対象期間が3ヶ月を超える時は、
この限度時間を設定できる範囲には次のような制限があります。
(ただし、積雪地域の建設業の屋外従業員等に対する1年単位の変形労働時間制については
制限がありません。)
1 対象期間名中に、週48時間を超える労働時間を定めるのは連続3週間以内とすること。
2 対象期間を初日から3ヶ月ごとに区切った各期間
(3ヶ月未満の期間がある場合にはその期間)において、
週48時間を超える労働時間を定める週の初日の数が3以内であること。
【割増賃金の支払い方は?】
労働時間が法定労働時間を超えた場合には、
その超えた時間について割増賃金を支払うことが必要です。
次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
1 1日の法定時間外労働
労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2 1週の法定時間外労働
労使協定で1週40時間を超える時間を定めた日はその時間、
それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(1で時間外労働となる時間は除く)
3 対象期間の法定時間外労働
対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて
労働した時間(1または2で時間外労働となる時間を除く)
【途中採用者・途中退職者等の賃金精算】
対象期間より短い期間労働した者に対しては、
使用者はこれらの従業員が実際に勤務した期間を平均して
週40時間を超えて働いた時間に対して、
次の計算式により割増賃金を支払うことが必要です。
割増賃金の精算を行う時期は、途中採用者の場合は対象期間が終了した時点、
途中退職者の場合は、退職した時点となります。
なお、転勤等により対象期間の途中で移動により労使協定の対象となった場合や、
逆に対象外となった場合についても精算が必要になります。
割増賃金を支払う時間 = 実勤務期間における実労働時間
- 労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金の支払いを要する時間
- (40×実労働期間の暦日数÷7)
上記【割増賃金の支払い方は?】の1、2で解説した、
1日・1週の法定労働時間外労働に該当する時間を指しています。
【育児を行う者等に対する配慮】
1年単位の変形労働時間制を導入する場合においても、
育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者
その他特別の配慮を要する者については、
これらの者が育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければならないとされています。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
1ヶ月単位の変形労働時間制の概要は?
【1ヶ月単位の変形労働時間制とは?】
1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、
その変形期間においては、1日及び1週間の法定労働時間
(1日8時間、1週40時間(特例措置対象事業場は44時間))の規制にかかわらず、
法定労働時間を超えて労働させることができる労働時間制です。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるもの、
または労使協定により導入することができます。
【要件】
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合には、就業規則等または労使協定により
次の1~4の要件を具体的に定める必要があります。
1 変形労働時間制を採用する旨の定め
2 労働日、労働時間の特定
変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めなければいけません。
各日の労働時間は、単に「労働時間は1日8時間とする」という定め方ではなく、
長さの他、始業及び終業の時刻をも具体的に定め、かつ、
これを従業員に周知しなければいけません。
変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても、
使用者が任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しません。
3 変形期間の所定労働時間
変形期間の労働時間を平均して1週間の労働時間は
法定労働時間を超えないこととされているため、
変形期間の所定労働時間の合計は、
次の式によって計算された範囲内とすることが必要となります。
法定労働時間×変形期間の暦日(1ヶ月以内)÷7(1週間)
これによって計算すると、例えば1ヶ月の場合、労働時間の総枠は次のようになります。
31日の月 ⇒ 177.1時間
30日の月 ⇒ 171.4時間
29日の月 ⇒ 165.7時間
28日の月 ⇒ 160.0時間
※ 労働時間の総枠は法定労働時間を週40時間として計算し、
小数点第2位以下を切り捨てて算出しています。
※ 例措置対象事業場の場合は、上記計算式の法定労働時間を
44時間として計算したものが、変形期間の労働時間の総枠となります。
4 変形期間の起算日
変形期間の始期を明らかにしなければいけません。
【就業規則等と労使協定について】
1 就業規則等
常時従業員を10人以上使用している事業場については就業規則の作成義務があるため、
その事業場が1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、
就業規則に前述の1~4の要件を記載し、従業員に周知するほか、
就業規則(変更)届を所轄労働基準監督署に届け出なければいけません。
従業員常時9人以下の事業場については、就業規則の作成義務がないので、
就業規則に準ずるものに規定することにより1ヶ月単位の変形労働制を採用することができます。
この場合、「就業規則に準ずるもの」を従業員に周知しなければいけません。
2 労使協定
労使協定を締結する場合には、次の4点について協定し、従業員に周知するほか、
所轄労働基準監督署に届け出を行う必要があります。
1 変形期間と変形期間の起算日
2 対象となる従業員の範囲
3 変形間中の各日及び各週の労働時間
4 労使協定の有効期間
なお、常時10人以上の従業員を使用する事業場が労使協定を締結し届け出を行う場合には、
就業規則(変更)の届け出も必要となります。
【割増賃金の支払い方は?】
労働時間が法定労働時間を超えた場合には、
その超えた時間について割増賃金を支払うことが必要です。
次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。
1 1日の法定時間外労働
就業規則等または労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
2 1週の法定労働時間
就業規則等または労使協定で1週40時間を超える時間を定めた日はその時間、
それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(1で時間外労働となる時間は除く)
3 対象期間なの法定時間外労働
対象期間の法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて
労働した時間(1または2で時間外労働となる時間を除く)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
業務中の事故でケガをした社員の通院時間は労働時間か?
業務中に発生した事故が元でケガをした社員が、
勤務時間中に通院をする場合、病院への移動時間や診察時間は労働時間となるのでしょうか。
労働時間とは、一般的には使用者の指揮監督の下にあることを意味しており、
必ずしも実際に働いているかどうかは問われません。
例えば、トラックの運転手が荷物の到着を待ってトラック内で待機している場合や、
トラック内で運転手が二人いて、助手席に座っている人が休息していたり、
仮眠をとっている場合等は「手待ち時間」と言い、労働時間の一種とされています。
手待ち時間と休憩時間。似たような概念ですが、その違いは下記の通りです。
手待ち時間:使用者の指揮監督の下にある(従業員に時間の自由利用が保障されていない)
休憩時間:使用者の指揮監督の下にない(従業員に時間の自由利用が保障されている)
「休憩時間とは単に作業に従事していない手待ち時間を含まず、
労働者が権利として労働から離れることを保証されている時間の意であって、
その他の拘束時間は労働時間として取り扱う」
という通達も出ています。(昭和22年9月13日 発基第17号)
冒頭の質問について検討しますと、業務中に起きたケガ(労災)という点がポイントです。
これがプライベートのケガであれば、私用外出の一環ですから、
当然労働時間に含める必要はありません。
業務中のケガの場合は、どのように考えるかと申しますと、
実は、プライベートのケガと同じです。
業務上の災害(労災)に対し、どのような補償をするかという問題と、
業務上の災害のための通院時間を労働時間に含めるかどうかは別問題です。
業務上の災害のための通院時間は、使用者の指揮監督の下にあるとは言えませんし、
従業員に時間の自由利用が保障されているのでしょうから、
これは手待ち時間ではなく、休憩時間です。
したがって、労働時間に含める必要はありません。
なお、労働基準法は最低限の基準を定めた法律です。
業務上の災害のための通院時間を労働したものとみなして賃金を支払うというのは、
法を上回る措置となりますので、問題ありません。□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
労働時間の適正な把握のために会社がすべきこと
先日、厚生労働省より、
『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準』
というパンフレットが公表されました。
そのパンフレットに、始業・終業時刻の確認(記録)の方法についての記載がありました。
該当部分を読みやすいように若干改変した上で、
皆様にご案内申し上げます。
1 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、
原則として次のいずれかの方法によることとされています。
(ア)使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
(イ)タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。
(ア)について
「自ら現認する」とは、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、
直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
なお、確認した始業時刻や終業時刻については、
該当労働者からも確認することが望ましいものです。
(イ)について
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基本情報とし、
必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、
使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを
突き合わせることにより確認し、記録して下さい。
なお、タイムカード、ICカード等には、
IDカード、パソコン入力等が含まれます。
2 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
その2の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、
以下の措置を講ずることとされています。
(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、
労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて
十分な説明を行うこと。
(イ)自己申告により把握した労働時間が
実際の労働時間と合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施すること。
(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で
時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の
定額払等労働時間に係る事業場の措置が、
労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因と
なっていないかについて確認するとともに、
当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。
自己申告による労働時間の把握については、
あいまいな労働時間管理となりがちであるため、
やむを得ず、自己申告制により始業時刻や終業時刻を
把握する場合に講ずべき措置を明らかにしたものです。
(ア)について
労働者に対して説明すべき事項としては、基準で示したもののほか、
自己申告制の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより
不利益な取扱いが行われることがないこと、などがあります。
(イ)について
使用者は自己申告制により労働時間が
適正に把握されているか否かについて定期的に実態調査を行い、
確認することが望ましいものです。
特に、自己申告制が適用されている労働者や労働組合等から、
労働時間の把握が適正に行われていない旨の指摘がなされた場合などには、
このような実態調査を行って下さい。
(ウ)について
労働時間の適正な申告を阻害する措置としては、
基準で示したもののほか、
職場単位ごとの割増賃金に係る予算枠や
時間外労働の目安時間が設定されている場合において、
その時間を超える時間外労働を行った際に賞与を減額するなど
不利益な取扱いをしているものがあります。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
出張の際の移動時間は労働時間か?
普段は東京で働いているのに、明日は大阪出張。
大阪に行くだけで数時間を要してしまいます。
こうした出張に伴う移動時間は労働時間としてカウントすべきなのでしょうか?
これは、移動時間をどのように過ごさせたかという実態により、答えが変わります。
具体的な労働義務がなく、移動時間中をどのように過ごすのかが自由であれば、
労働時間ではないと判断しやすくなります。
一方、例えば自社の商品を無事運ぶために、移動中についても監視を命じた出張や、
自社の商品等を運搬すること自体を目的とした出張である場合、
移動中に自由に持ち場を離れることはできなくなり、
万が一商品等が盗難にあったり、損傷したりした場合は、就業規則等の定めにより、
制裁を科されることも考えられます。
こうなってくると、会社の指揮監督下にあるとみなされ、
移動時間中も労働時間であると判断されやすくなるでしょう。
なお、出張中の休日について、以下のような通達が出ております。
出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、
旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は
休日労働として取り扱わなくても差し支えない。
(昭和23年3月17日 基発第461号、昭和33年2月13日基発第90号)
こうしたことから、会社側の立場としては、
移動時間を労働時間としないようにするために、
次の点にお気をつけください。
★ 移動時間中に○○の業務をしなさい、などという業務指示を出さないこと
★ 移動時間中、物品の監視をしなければいけない等、
移動時間中も必然的に業務となってしまうような事態を避けること
逆にこうしたことが満たされない場合は、労働時間としてカウントすることが原則となります。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
職場に火災発生!善意で職場に駆けつけ消火活動をした時間は労働時間?
職場に火災が発生した場合、既に帰宅している従業員が、
任意に職場に出勤し、消火作業に従事した時間は労働時間でしょうか?
昭和23.10.23基収3141号、昭和63.3.14基発150号によると、
一般に労働時間とするとの見解です。
出勤命令が出て消火作業に従事すれば、当然労働時間ですが、
こうした場合、従業員の任意であり、上司からの指示・命令もなく消火作業をしたとしても、
労働時間としてカウントしてよいということです。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
自社の従業員を休日にアルバイトさせることってできますか?
例えば、土日が休みの会社があるとします。
Aという部署が忙しく、人手が足りないので、
Bという部署のメンバーに声をかけて、
希望者には土日に「アルバイト」として働いてもらうことはできるのでしょうか?
1 雇用契約上の問題
雇う側の会社も、雇われる側の従業員も同一であるにもかかわらず、
平日は正社員として雇用契約を結び、
休日はアルバイトとして別個の雇用契約を結ぶというのは
理論的にはありえますが、
実態は一体のものとして取り扱うべきものです。
そうしなければ、どこの会社も休日は「アルバイト」扱いにすることで、
休日出勤が休日出勤でなくなってしまいます。
これでは労働基準法が骨抜きとなってしまい、法の趣旨に反してしまいますので、
認められないわけです。
さらに、労働時間は、事業場を異にする場合においても、
労働時間に関する規定の適用については通算するという定めがあります。
(労基法38条第1項)
したがって、仮に1日の所定労働時間が8時間の会社であれば、
平日5日分で週の法定労働時間40時間となりますので、
土日のどちらかに出勤した時点で1.25倍で計算することになりますし、
その日が法定休日であれば、1.35倍で計算することになります。
2 残業単価
昭和23年11月22日基発第1681号には次のような説明があります。
所定労働時間中に甲作業に従事し、
時間外に乙作業に従事したような場合には、
その時間外労働についての「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは、
乙作業について定められている賃金である。
ここから、休日労働での作業に対して
普段の仕事とは別の賃金が割り振られている場合は、
休日労働の作業に見合った賃金を元にした残業単価で計算すればよいということになります。
まとめ
1 雇用契約上は、二つの雇用契約を走らせるのは無理がある。
2 労働時間は平日の業務と通算して計算しなければならず、
その上で、割増賃金が発生する場合は、割増賃金を支払わなければならない。
3 ただし、残業単価はその作業に見合った賃金が設定されている場合は、
その賃金を元にして計算して構わない。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
不正受給していた手当を今後支払う給与と相殺してもよいか?
本来利用していない交通機関を利用していることにして、
通勤手当を不正に受給していた社員がいた場合、
今まで不正に受給していた金額を給与から控除してもよいのでしょうか?
方法論と注意ポイントは次の通りです。
1 会社側で一方的に相殺しようとする場合
★ 従業員代表と、不正受給した金額を控除できる旨の労使協定を締結すること。
★ 一支払期の賃金あるいは退職金の4分の1までしか相殺できないことに注意すること。
賃金については「全額払いの原則」があります。
賃金の計算期間に対する労働に対する対価については、
全額を労働者に支払わなければいけません。
一部しか支払わないと、不当な引き留め工作となる場合があり、
従業員を拘束してしまったり、生活を不安定・困窮させてしまう恐れがあるためです。
ただし、例外として、次の二つのどちらかであれば、給与から控除してもよいこととなっています。
1 法令で控除してもよいものとされている控除項目(例:所得税、住民税、社会保険料)
2 労使協定を締結した控除項目(例:労働組合費、社内旅行積立金 等)
今回も給与から控除するわけですが、「1」には該当しませんので、
「2」の要件を満たすべく、労使協定を締結することになるわけです。
ただ、支払額については、民法第510条、民事執行法第152条により、
一支払期の賃金あるいは退職金の4分の1までしか控除できないことになっておりますので、
ご注意ください。
2 従業員側で賃金の相殺に同意した場合
★ 従業員の完全な自由意思に基づくのであれば、控除可能。
★ 一支払期の賃金あるいは退職金の4分の1までしか相殺できないという制限を受けません。
従業員の同意を得られれば、従業員と同意した額を賃金から控除することができます。
ただ、当然のことながら、会社側としては会社側の一方的な相殺となると、
労使協定書を締結する手間がかかりますし、しかも相殺できる額にも制限がありますから、
無理やりにでも従業員に同意させて、一気に清算させることを検討することになろうかと存じます。
こうなると、悪いことをしたのは従業員とはいえ、
その従業員の自由意志と生活を守らなければならない、という側面との
バランスを取る必要があります。
そこで、相殺することが従業員の自由意思に基づくものと
客観的に認められる合理的理由の存在が要件となっているのです。
当然のことながら、口約束だけではトラブルになった時に弱くなりますので、
ご本人との約束を書面に残すことは最低限しておいた方がよいでしょう。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
休業期間中の休日についての平均賃金を算出する際の取り扱い方
平均賃金の算定期間中に会社側の責任とされる事由により
休業した期間がある場合、
その日数及びその期間中の賃金は、
平均賃金算定の基礎となる期間及び賃金の総額から
控除することとされています。
(労働基準法第12条第3項第3号)
この場合、休業期間中に、
労働協約、就業規則、または労働契約により
休日と定められている日が含まれている場合、
この休日の日数は、休業した期間の日数に含むものとして計算します。
なお、休業の開始日及び終了日は、
この休業に係る労使協定や
就業規則の規定に基づく会社の指示等により、
個別の状況に応じて客観的に判断することになっています。
(平成22年7月15日基発第0715号第6号)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
給料(給与、賃金)を銀行に振り込みすることは通貨払いの原則に違反しているのか?
給料や残業代などの賃金は通貨で支払うことが原則です(労働基準法第24条)。
通貨で支払うということは、現金で支払うということです。
昔の映画を見ると、給料日に経理の人が一人一人の差引支給額を給料袋に入れ、
上司や社長さんが「今月もお疲れ様!」と、
現金の入った給料袋を渡すシーンがあります。
労働基準法の世界では、こういったことが今でも原則なんです。
一方、21世紀の現代、こうした賃金は、
大半の企業では、金融機関への振込によって支払われています。
銀行振込というのは、法的に言うと、
「従業員が金融機関に対して預金を引き下ろす債権を取得した」
ということです。
現金を支給されたことにはならないのです。
しかし、現代では電気やガス料金、電話代、学習塾の授業料等、
様々なものが口座から引き落としされる世の中になっており、
銀行預金は生活と切り離せないものになっています。
また、現金でもらうよりも銀行振込の方がお金の管理がしやすいですよね。
さらに、経理の人も、給料を渡された人も
多額の現金を持ち歩く必要がなくなるので、安全性が高いのです。
したがって、振込が通貨払いの原則に違反していると考えるのは、
現実的ではなくなっているのです。
そこで、従業員の同意がある場合には、
従業員が指定する金融機関の口座への振込の方法によって
賃金を支払うことも許されるとされています(労働基準法第7条の2第1項)。
また、通常の預金口座以外にも、証券口座(MRF)に
振り込むことも許されるとされています(同条第2項)。
なお、この場合の「同意」は
従業員の意思に基づくものである限り、
その形式は問いません。
また、「指定」とは、
従業員が賃金の振込対象として金融機関に対する
従業員本人名義の預貯金口座を指定するという意味であり、
この指定が行われていれば、特段の事情がない限り、
従業員の同意を得たと考えてよいとされています。
(昭和63年1月1日 基発1号)
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■
有期雇用契約者と解雇制限
5日間の有期雇用契約を締結して、働き始めたAさんが、
初日、荷物を運搬中に大けがをしてしまいました。
本人は現在入院中。
そんな時パラパラと労働基準法の解説書を読んでいると、
こんなお約束があることに気がつきました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
使用者は、次の場合、それぞれ定める期間、解雇してはいけません。(労働基準法第19条)
★ 労働者が業務上ケガや病気にかかり療養のために休業する期間 & その後30日間
★ 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間 & その後30日間
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
この有期雇用契約者、有期雇用契約期間が終わっても、
休業期間中雇用し続けることはもちろんのこと、
復帰も認め、さらに30日間は雇用し続けなくてはいけないのでしょうか?
実は、この条文は期間の定めのない従業員の方を想定した条文です。
したがって、有期雇用契約者の場合は、この条文は適用されませんので、
期間満了時に、当然に労働契約は消滅します。
なお、例え5日間のアルバイトであっても、労災は適用されます。
こちらは手続きをするのを忘れないよう、ご注意ください。
□■□□■■□□□■■■□□□□■■■■□□□□□■■■■■□□□□□□■■■■■